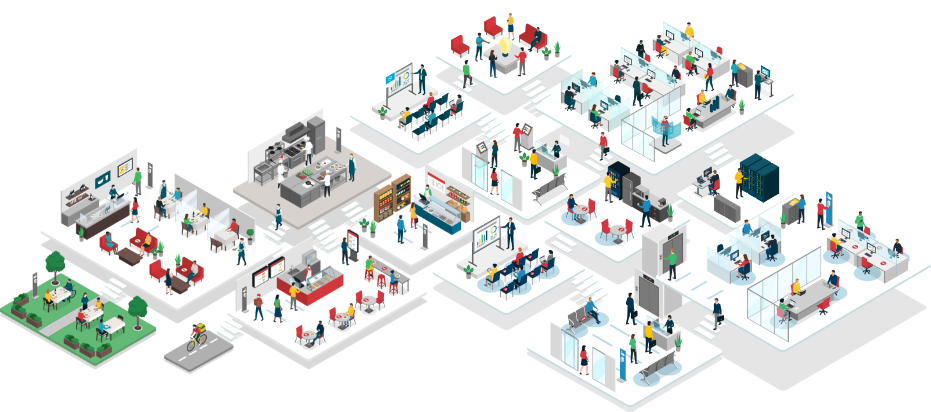ストーリーがあるケータリング
============================================

最近、出社率の増加を受けて、社内コミュニケーションを活性化させる取り組みとして「ケータリングサービス」を導入する企業が増えています。
ケータリングとは、一般的に食事を配膳・提供するサービスのことを指しますが、現在ではそのスタイルも多様化し個性豊かなサービスが次々と登場しています。
中でも、際立った存在感を放っているのが「良品計画のケータリングサービス」です。良品計画といえば、生活の基本商品が揃う「無印良品」を展開する企業として、多くの方に認知されています。その事業領域は幅広く、食に関しても地域やコミュニティの活性化を目指して、さまざまな取り組みを行っています。
その良品計画が提供するのは、単なる食事ではない、“ストーリーのあるケータリング”。食を通じて人と人をつなぎ、企業文化や価値観を共有する場を創出することを目指しています。
今回は、この”他にはない”ケータリングサービスがどのように誕生したのか、そしてその魅力や可能性について、企画・開発を担当した松木さんにお話を伺いました。
サービスの原点は各地で起きている課題から
==============================================

―良品計画のケータリングサービスの魅力について教えてください。
良品計画が展開するケータリングサービスには、他にはない大きな特徴があります。それは「食べることを通じて地域や環境に貢献できる」という点です。
安心・安全な食材を使用し、素材本来の美味しさを届けることはもちろん、メニューには環境に配慮した食材が積極的に取り入れられています。これにより、土壌や水質などの自然環境の改善に寄与しながら、地域の課題解決にもつながる取り組みとなっています。生産者と産地の両方を守ることができる、持続可能な食のあり方を体現しています。
その象徴的なメニューのひとつが、「アイゴのフライ」です。アイゴは海藻を餌とする魚で、近年の地球温暖化による海水温の上昇により、その活動が活発化していることで藻場が食べ尽くされる「磯焼け」現象が深刻化しています。磯焼けは海藻類の衰退・消失を引き起こし、魚の生息地が失われることで海の生態系バランスが崩れ、漁獲量にも悪影響を及ぼしています。
さらにアイゴは、毒を持つことや、漁獲後に臭みが出やすい性質から、食品としての流通が難しいという課題も抱えています。そこで良品計画は、このアイゴを美味しく食べながら海の環境を守る方法として「アイゴのフライ」を開発しました。シンプルな味付けで素材の旨味を引き出し、ケータリングメニューとして提供することで、海の問題に関心を持つきっかけをつくっています。
小さな一歩が大きな変化へ
==============================================

無印良品の商品として一般流通させるには、厳しい検査や長い準備期間が必要ですが、ケータリングであれば比較的柔軟に提供が可能です。食を楽しみながら環境課題に触れることができるこの取り組みは、やがて大きな成果へとつながる可能性を秘めていると感じています。
良品計画のケータリングは、単なる食事の提供にとどまらず、地域と環境を守る新しい食の形を提案しています。
―良品計画の中でケータリングサービスを立ち上げたいという想いはどこからきたのでしょうか?
もともと「食と農」を通じて地域やコミュニティを活性化する取り組みを推進する部門に異動してから、ずっとケータリング事業への想いを温めてきました。
千葉・鴨川にある「里のMUJI みんなみの里」という交流施設の立ち上げと運営を任されたとき、現地のスタッフや農家さんと一緒に、山や海、酪農など、自然の魅力とその裏にある課題に向き合う日々を過ごしました。そうした体験を通じて、生産の現場には、外からは見えにくい問題がたくさんあることを実感したのです。
施設の運営が軌道に乗ってきた頃、「食」にまつわる課題を、良品計画としてもっとスピーディーに、そして実践的に解決できる方法はないかと考えるようになりました。そこで、以前から心の中で温めていた「ケータリング」というアイデアが、農家さんを支えるヒントになるかもしれないと思い、社内で手を挙げました。
環境問題が深刻化する中で、農家さんの高齢化や地域の過疎化が進み、経営が厳しくなって、1年以内に廃業してしまうケースもあります。農家さんにとって、半年や1年という時間は、事業の存続を左右する本当に大切な期間なのです。
その限られた時間の中で、良品計画の知名度やブランディング力を活かして、少しでも早く支援につなげる手法として、「ケータリング」はとても有効だと感じました。
―なるほど、ケータリングのメニューとして直接食材を使うことができれば農家さんをダイレクトに、スピーディーに支援できるということですね!温めていた想いが形になるまでにどれくらいかかりましたか?
そうですね、構想段階から3年ほどかかりました。信頼できる仲間を集め、サービスとして構築するために様々な産地に出向き、話をじっくり聞いて進めました。
その取り組みの積み重ねが少しずつ実を結び、今では生産者の方々と産地、そして良品計画が一緒になってつくり上げた、私たちらしい“食の形”が社内でも徐々に認知されるようになってきました。社内協力も増え、ESGやCSRに関心のある企業様を通じて、外部にも広がり始めています。各企業様の会合主旨にあったメニューをご提案しつつ、お時間があればメニューにまつわる農業、林業、漁業で起きている問題についてもお話させていただく機会もあります。
―まさに「想いを伝えるケータリング」ですね。
良品計画ならではの「ストーリー」を今後どのように伝えていきたいと思っていらっしゃいますか?
いつか、食をきっかけに産地や作り手に興味を持ってもらい、実際にその土地を訪れてもらえるような、ケータリングの枠を超えた企画に挑戦してみたいと思っています。
たとえば、生産者の方と消費者が直接話せるような場をつくることも、ぜひ実現してみたいアイデアのひとつです。顔の見える関係性が生まれることで、食の背景にあるストーリーや想いがもっと伝わるようになれば嬉しいですね。
―本日は、ありがとうございました。
知っておいしい、無印良品のケータリング
松木 健太郎
入居の窓口サイトはコチラ